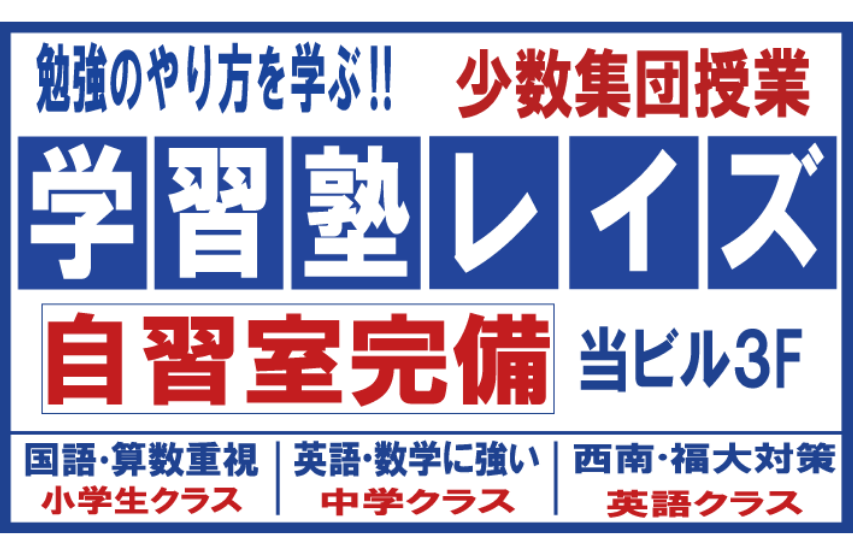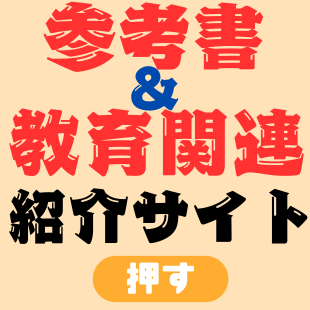高校になってから国語・英語が難しく感じる原因の一つには抽象的な語彙が増えたことにあります。
なぜ、抽象的な言葉が増えたら難しく感じるのか、簡単に書いておきます。
抽象的な単語が難しい理由
抽象的な言葉が難しのは以下の3つに理由があります。
イメージしにくい
具体的なこと、例えば、「赤いリンゴ」と聞いたら
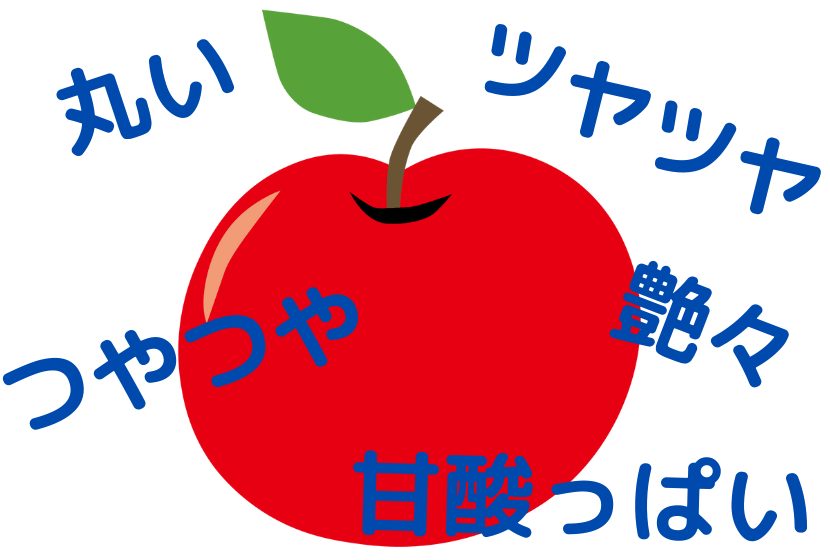
丸くて、つやつやしていて、甘酸っぱい匂いがするリンゴを頭の中に思い浮かべられるはずです。
これは、色や形、味、匂いといった具体的な情報があるからです。
一方、「正義」という抽象的な言葉を聞いても

どんな形をしているか、どんな味がするかわかりません。
「正しいこと」という意味は分かるけど、人によって思い描く「正しいこと」は違うかもしれませんん。
このように、具体的なイメージがわかないから、捉えどころがなくて難しく感じるわけです。
経験と結びつきにくい
たとえば、「犬が散歩している」という文にを読んだときはどうでしょうか?
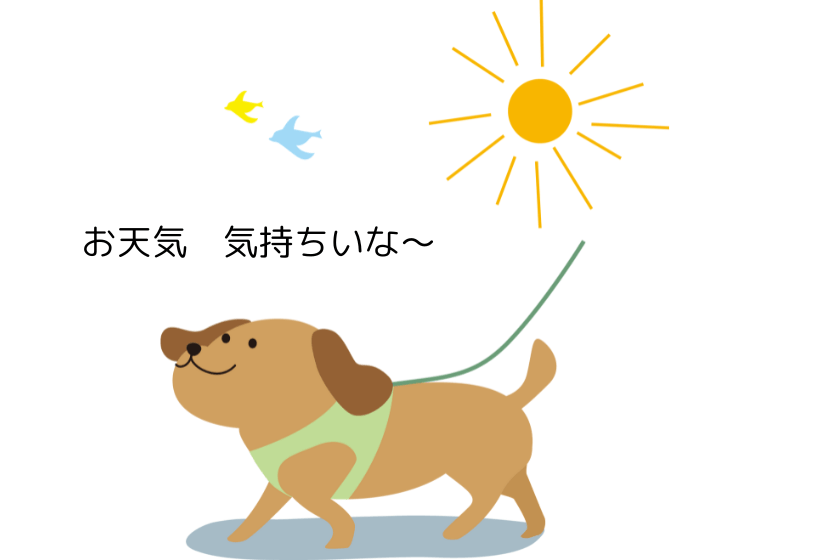
犬が飼い主と歩いている姿を実際に見たことがない人はいないはずなので、自分の経験と結びつけて、「ああ、公園でよく見る光景だな」というように理解できます。
一方、「自由」はどうでしょうか?

「自由」という言葉は知っていても、「本当に自由な状態ってどんな感じだろう?」と、自分の経験と結びつけにくはずです。
経験したことがないことや、目に見えない概念は理解するのに時間がかかるるわけです。
一義的に決まらない
抽象的なことは説明が広範囲になりやすいです。
たとえば、「このペンは青い」と言えば、それだけで誰にでも伝わるので、説明が一つで済みます。
ところが「平和の大切さ」を説明しようとすると、「戦争がないこと」「人々が安心して暮らせること」「差別がないこと」…といろいろなことを説明する必要が出てきます。
一つの言葉で色々な意味を含む抽象的な言葉は、説明が広範囲になるから、全体像を掴みにくくなります。
どうすれば読めるようになるのか
内容が抽象的で捉えにくいと感じるときは
- キーワード
- 筆者の主張
- 対比
- 具体例
- 原因・理由と結果
- 背景知識
これらを意識しながら読むことが重要です。
中学校のときは、文章内容が平易であったため、これらを意識せずとも読解できていたかもしれません。
しかし、それは難しい文章を読む力が元々備わっていたのではなく、「読める」と錯覚していたに過ぎません。
難しい文章を読解できるようになるためには、どこに注意して読めばいいか意識をながら、日頃から多くの文章に触れ慣れていくことが大切です。
現代文も英語も、そうすることで、最初は難解に感じられる内容でも、徐々に理解できるようになっていくはずです。
もちろん、西南学院大学や福岡大学レベルの大学を受験するのであれば、学校の授業で扱われる文章を読むだけでも十分対応できます。
しかし、国立大学の二次試験や難関私立大学の入試問題をある程度解けるようになるためには、学校の授業とは別に、高校1・2年生の段階で一定以上の文章に触れておくことが、合否を大きく左右すると思ってください。
国立の受験科目は7科目くらいあるのが通常なので、それらすべてを高校3年の1年間でやろうとするのは無謀です。
無謀というより不可能です。
これは国立理系学部を受験する場合も同様です。
国立の理系学部は二次試験に英語・国語を課さないところも多くあるので、受験期は数学・理科に勉強時間の大半を注ぐことになると思います。
このとき、この2科目を初めから捨てる受験生が少なからずいます。
そんな中、高校1・2年の時に英語・国語にある程度時間をかけ共通テストで7割くらい取れる実力になっていれば、かなりのアドバンテージをえられ、合格に近づきます。
現代文・英語で抽象的な文を読むときのコツ・ヒント