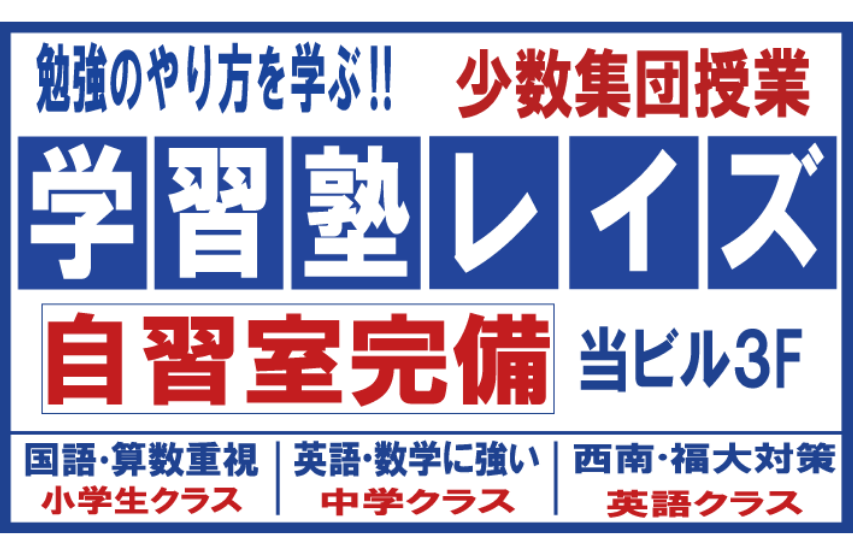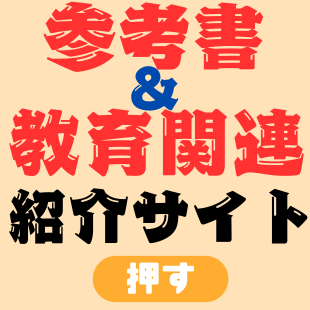2020年ころから漫画・アニメのすごさに惹かれて、おじいさんと言われるような年齢になってからオタクになった私ですが
漫画・アニメの中には明らかに勉強になるものがあるわけです。
学校で習う5教科の勉強も大切ですがVUCA時代、学校の勉強ばかりやっていては大人になったときに「それAIでできるから。で、君は何ができるの?」と
2020年代に学校で身につけた知識・技術が一切加工されないままの単なる知識・技術としてしかないと、将来が危ういわけです。
じゃあ、子どもたちは大人になる前の今何ができるか?
と問われると、スポーツ・芸術・音楽・生活といった、ありきたりなものしかなく
そこに自分がハマれるものがあればラッキーですが、そう簡単に「これずっとやっていられる」と思えるものは見つからない分けです。
今までは、とりあえず将来のために勉強をしようという子がある程度の割合がいたわけですが
今やったことが将来どのように活きるかが全く分からないVUCA時代、勉強をする意味を感じにくくなった社会
加えてユーチューブ、tiktokといった動画サイトの存在により、それらを受け身的に消費するだけの子が大多数を占めてしまっている状況にあります。
2000年代前半頃までの、「勉強をしていい大学に入ればとりあえず何とかなる」というのが日本人の共通理解だったときがどれだけ楽だったか…。
勉強だけしてもダメ、やりたいことをやろうにもそれが見つからない、見つからないどころか無料で消費できる娯楽が多くてその勉強すらやろうとする精神を保つことも難しい。
今の子供たちは、今現在30~50代の親世代と比べ、厳しい世界に放り込まれてしまっているわけです。
そこで、私が勧めたいのが
漫画・アニメを楽しむ
ということなんです(他に打ち込んでいるものがあれば無理に漫画・アニメは必要はありません。あくまでも学びの一つとして利用できるというだけです)。
消費する
ではなく
楽しむ
です。
例えば「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」というアニメがあるんですが、
これ一般的な感覚からすれば
「あ~、中高生がみそうなやつだわ、大人が見るなんてありえない。見ている人がいたらちょっと引く」
なんて思われてしまうかもしれませんが(私も2020年以前はそう思っていました。しかし、学校の勉強以外で子どもたちが学べるものは何かということを考えた時に、漫画にたどり着き、その後アニメも意識的に見るようになっていきました。VUCA時代を生きる子どもたちが、やりたいことを見つけるためには、気軽に読んだり・見たりできるアニメは、5教科の勉強と同じくらい重要なものになり得ます)
意外とそうでもないんです。
何も考えずに見れば、どう考えても、こんなアニメを大人が見たら気持ち悪いと思われても仕方がないのですが、映像やキャラのやり取りの恥ずかしさはとりあえず置いてください(いや、繰り返しますが2020年以前の私がこんなアニメを観ている大人を見たら絶対に引いていました。でも、今は恥ずかしいとかの前に、どんな方法を使ってでも、学校の勉強だけ、受け身的に何かを消費するだけといった状況にいる子どもたちに、様々なことに目を向けてもらいたいということが強いので、「こんなアニメを見ているの?」と思われる恥ずかしさを捨てて、漫画・アニメも学びに繋がるということを書いています。あえて映像と内容が極端な青ブタを選んだのは、ぶっ飛んだものを例にすることで目を引かせるためで、どんな漫画・アニメでも学びに繋げることは可能です。漫画・アニメはごまんとあるので、まずは自分のお気に入りの物を探してそれを学びに繋げてみて下さい)。
これ、実はSF要素が強い作品で
物語の核心である「思春期症候群」は、量子力学の理論で説明しようとするんです。
作中では、ヒロインの一人が周囲から見えなくなる現象が起こるんですが
これは「観測するまで、ものの状態がはっきりと決まらない」という量子力学の考え方で説明されます。
思春期の不安定な心理状態が、自分自身の存在を「観測」することを拒み、量子を不確定な状態にした結果、見えなくなってしまったという設定です。
こんな感じで見ると、アニメも勉強になるような気がしませんか?
このアニメを子供が観る前に「ここで起こっている不思議な現象って『量子力学』っていうことが影響しているんだって」
というように、どこに注目するかを伝えておけば、
アニメを通じて「量子力学って何だろう?」と興味を持つかもしれません。
それが関連書籍を読み始めるきっかけになり
例えば、『現象が一変する「量子力学的」パラレルワールドの法則』なんかを読むようになる可能性だって出てきます。
難しそうなタイトルですが面白そうにに関心があれば中学生でも十分に読める内容なっているので、読みを得るころには数学・物理に関心を持ち始める・・・
なんてこともなくはありません。
漫画やアニメを能動的に楽しむことで、学びとは無縁と思っていたアニメですら学びに繋がるキッカケになっちゃうんですね(「虚構を通してものを考える」という表現を宇野常寛さんはされています)。
そして、能動的に楽しめば、学校では学ばないような知識が身に付くだけでなく、知識が増えたことによって自分でいろいろなことが考えられるようになり、過去に触れた作品を以前とは違った視点で見られるようにもなります。
作品を深く追求することができるようになり、それがさらなる学びに繋がるなんてことが当然のように起こっていくわけです。
将来何がどう役立つかわからないのだから、学校の勉強をして知識・技能を高めつつ、自分の興味関心の幅を広げ、やりたいことをやれるようにするために漫画・アニメを道具として利用しちゃいましょう。
それに、日本の漫画・アニメは文化としてこれから世界に広がる可能性もあります(実際に、ここ数年で漫画・アニメがどんどん世界に広がりビジネス規模は拡大し続けています。ただ3Dアニメが世界の主流になってしまうと、日本のアニメがガラケーのようにガラパゴスかしないとは言えないですが)。
漫画・アニメを深く知ることで世界を対象にビジネスができるかもしれないのだから、「漫画・アニメ」とバカにするなんてもったいないです。
21世紀の現在、源氏物語が古典として学ばれているのと同じように、漫画・アニメが数百年後勉強の教材になることも十分考えられます。