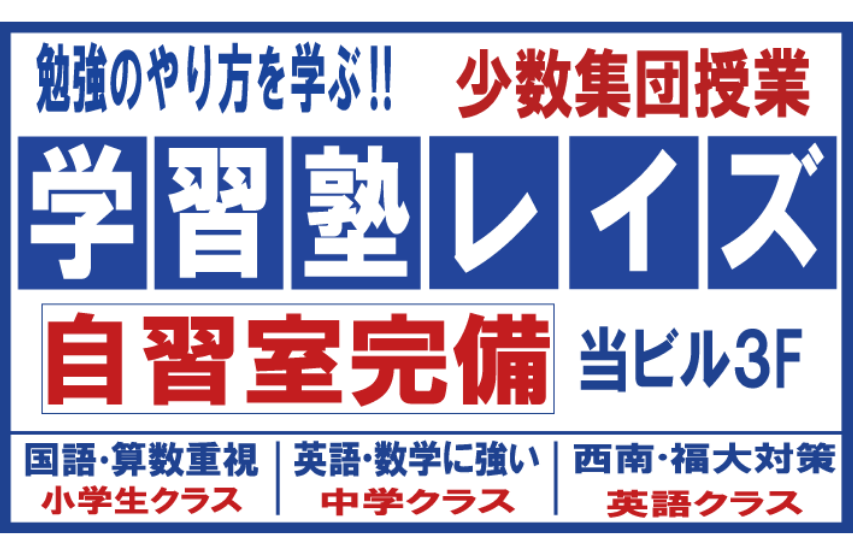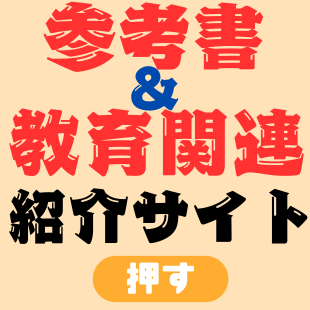レイズではすべての科目の中で国語が一番重要な科目だと考えています。
目次
国語は一番重要な科目
映像授業・AIを活用し、講師一人で多数の生徒を見る個別指導塾が増えています。
確かに、与えられた知識を習得するだけであれば、映像授業でも十分かもしれません。
しかし、自ら学び続ける力を身につけるためには、学習方法そのものを学ぶ必要があります。
そして、その最も効果的な手段が国語の勉強です。
小学生のうちに国語を通じて読解力、語彙力、思考力を徹底的に鍛えることで、将来、「能力がないから何もできない」といった状況を回避できます。
能力が高ければ高いほど、社会に出た際の選択肢は広がります。
このように重要な科目である国語ですが、中学校に進学すると、英語や数学に多くの時間を割かざるを得ず、国語学習に十分な時間を確保することが難しくなります。
だからこそ、小学生の今が国語学習の絶好のチャンスなのです。
なんとなく国語の勉強をして時間を無駄にするのではなく、実りある国語学習に取り組みましょう。
読む力(説明文)
文章を読むために必要な要素は、大きく分けて二つあります。
第一に、「豊富な語彙力」です。
難しい文章を一人で読みこなせるようになるためには、小学生のうちにできるだけ多くの語彙を習得しておくことが重要です。
日頃から言葉を覚えることへの関心を育むことで、文章読解の基礎を築きます。
第二に、「読解ルールの理解」です。
語彙力があっても、設問の意図を正確に捉え、解答を導き出す方法を知らなければ、的確な答えを出すことはできません。
指示語、接続語、抽象と具体、因果関係など、文章読解に必要な規則を習得します。
小学生のうちから「文章読解の訓練」と「語彙力を増やす訓練」を並行して行うことで、中学以降の学習をスムーズに進めるための基礎を固めます。
説明文の学習後には、題材に応じてブレインストーミングやKJ法などの手法を取り入れ、グループでの話し合いを行いたいとも考えています。
アイデアを出し合い、整理する経験を積むことで、思考力とコミュニケーション能力を高めます。
これらの学習を通して、単に学校の成績を向上させるだけでなく、自ら考え、抽象的に思考する力(1を聞いて10を知る力)を養います。
書く力
与えられた文章を深く理解し、自分の考えを表現できるようになることを目標とします。
ただし、自分の考えを自由に書くことは容易ではありません。
そこで、段階的なステップを踏んで、着実に力をつけていきます。
小学6年生の1学期は、まず短文の暗記から始め、それを作文用紙に書き写す「暗記作文」に取り組みます。
そして、6年生の2学期以降は、テキストの文章を自分の言葉で「要約」したり、「作文」したりする訓練を行います。
単に問題を解くだけでは、国語の力を十分に伸ばすことは難しいものです。
しかし、要約と作文の訓練を重ねることで、自分の成長を実感しながら、確実に力をつけることができます。
なお、作文のテーマは、「昨日遠足がありました。楽しかったです」といった単純なものではなく、課題文を読み、自分の考えを論理的に展開する形式とします。
漢字を大切に
表意文字である漢字は、例えば「屹立」のように普段使わないものでも、「屹」に「山」が含まれていることから、山のイメージが浮かびます。
そこから「山がそびえたつ」という「屹」の基本的な意味を覚えやすくなるはずです。
さらに、「山がそびえたつ」様子から、どっしりと重く動かないイメージが連想され、「確立して揺るがない」という意味も自然と記憶に残るでしょう。
「屹」のように日常的に使われない漢字を例に挙げましたが、普段よく使う漢字も同様です。
例えば、「佳」を見てみましょう。
「佳」には、「美しい」「立派だ」「称賛する」といった意味があります。
これらの意味を覚えておけば、「佳作」が「優れた作品」という意味であるとすぐに理解できます。
また、「佳器」「佳客」「佳話」など、見慣れない言葉でも、文脈と照らし合わせることで「良い器(立派な器)」「良い客」「良い話(世に広くもてはやされる美談)」といった意味を容易に推測できるはずです。
このように、漢字一つ一つの意味を理解することは、語彙力を高める上で非常に重要です。
そして、漢字の成り立ちや意味を紐解くことを面白いと感じられるようになれば、子どもたちは自然と学習に取り組むようになるでしょう。
小説を読む
瀬尾まいこさんの「あと少し、もう少し」の冒頭には、
おれがアンカーを走ることに決まったのは、今日の朝だ。
という一文があります。
この一文を文字通りに解釈すれば、「おれ」という一人称を使う人物が「今日の朝にアンカーを走ることが決まった」という事実を述べているだけに過ぎません。
しかし、多くの読者はこの一文から、それ以上のイメージを膨らませるのではないでしょうか。
例えば、「おれ」という一人称から、小学生、中学生、あるいは高校生の男子生徒を思い浮かべるでしょう。
少なくとも、女子生徒や50歳を超えた男性をイメージする人は少ないはずです。
さらに、「アンカーを走る」という行為から、足が速く、スポーツ万能で、目立つタイプの人物像を想像するかもしれません。
このように、小説を読む際には、文章に書かれていない情報も自然と頭の中にイメージとして浮かび上がってくるものです。
面白いのは、これらのイメージが人によって異なる点です。
私が上で述べたイメージは、あくまで一般的なものであり、実際には全く異なるイメージを持つ読者もいるでしょう。
例えば、走るのが苦手なのに無理やりアンカーに選ばれた気の毒な生徒を想像する人もいるかもしれません。
あるいは、「おれ」という一人称を使う女子生徒を知っている人が読めば、その人物をイメージする可能性もあります。
過去に同様の発言を父親から聞いたことがある人なら、50歳を超えた男性が運動会で急遽アンカーを頼まれた場面を想像するかもしれません。
このように、小説の解釈は読者によって多様です。
しかし、小説の読解問題を解く際には、唯一の正解を導くために、「心情表現」「人物描写」「情景描写」などを手がかりに読み進める必要があります。
そこでは、自分の解釈を挟む余地はありません。
小説には本来、作者が直接的には説明しないテーマがあり、読者は自由に解釈できるはずです。
しかし、読解問題では用意された正解を見つける作業が求められ、読書本来の楽しみが失われてしまいます。
そこで、レイズでは塾とは別に、不定期で読書会を開催し、読解問題を解くためではなく、参加者同士が自由に解釈を語り合う機会を設けることにしました。
子どもたちがこれをきっかけに本を読む時間が増えれば、文章を読むことに慣れていきますし、語彙力も自然と増やすことができるはずです。