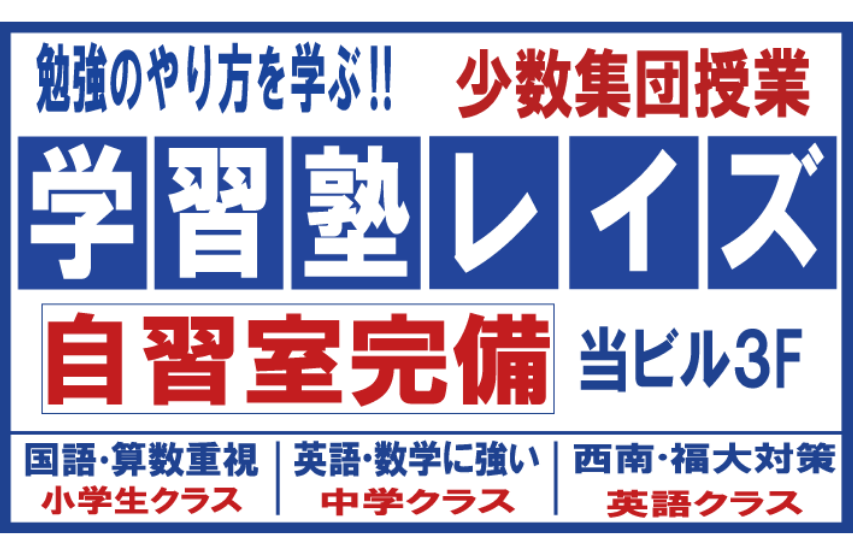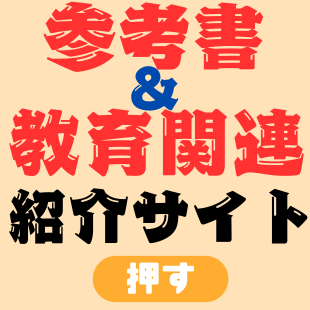九州産業大学の合格最低点は公表されていないません。
なので、どれくらい取れていれば合格できるのか分からず気になって仕方がない受験生が多いみたいです。
しかし「合格最低点は合否結果が出るまで不明」に書いた通り、受験後に何点取れば合格できるかどうか考えても意味がありません。
一応合格最低点について書きましたが、以下の内容は参考程度にしてください。
目次
難化前
九州産業大学の入試難易度が近年上昇している背景には、定員厳格化の影響が考えられます。
以前は一般前期入試において、倍率が2倍を超える学科は少なく、2010年以前は1.1倍から1.8倍程度に落ち着いていました。
そのため、「九州産業大学に合格できないのは、勉強不足ではないか」と揶揄されることもあり、Fランク大学と見なされることもありました。
しかし、ここ数年の入試倍率を見ると、理系学科を除いて3.0倍以上は当たり前となり、国際文化学部や人間科学部では5倍以上、時には6倍を超えることもあります。
この数字から明らかなように、九州産業大学はもはや誰でも合格できる大学ではありません。
2010年から2016年度の入試で福岡大学にぎりぎり合格していた層が、2018年から2021年度に九州産業大学を受験した場合、不合格になっていた可能性すらあります。
それほどまでに、九州産業大学の合格は難化していると認識すべきです。
難化は続くか
西南学院大学と福岡大学の2021年度入試は、過去数年間と比較して合格しやすい傾向が見られました。
この状況が今年も続くかは不透明であり、受験者数の変動によって倍率が上昇する可能性も否定できません。
しかし、近年続いた超難化傾向からは脱し、比較的合格しやすい状況が続くと考えられます。
一方、九州産業大学は事情が異なります。
難化傾向が落ち着き始めたと考えられる現在でも、志願者数の減少は見られません。
むしろ、難化以前と比較して大幅に増加した志願者数が維持されています。
このことから、九州産業大学の入試難易度は、今後も高い水準で推移する可能性が高いと言えるでしょう。
学部編成があり定員や学科が変わってしまったので正確に比較するのが難しいのですが
平成24年(2012年)度入試の一般前期の志願者数(合格者数)は
- 国際文化:127名(60名)ー2.1倍
- 日本文化:105名(50名)ー2.1倍
- 臨床心理:161名(49名)ー3.2倍
- 経済 :559名(306名)ー1.8倍
- 商学 :550名(290名)ー1.8倍
- 観光産業:112名(75名)ー1.3倍
- 国際経営:118名(76名)ー1.3倍
- 産業経営:129名(71名)ー1.4倍
- 情報科学:87名(71名)ー1.2倍
- 建築 :78名(53名)ー1.5倍
- 合計 :2,685名(1,690名)ー1.5倍
それが令和3年(2021年)度はどうでしょうか?
- 国際文化:476名(105名)ー4.5倍
- 日本文化:320名(63名)ー4.9倍
- 臨床心理:553名(92名)ー5.9倍
- 経済 :2077名(476名)ー4.0倍
- 経営管理:1135名(386名)ー2.9倍
- 流通 :982名(249名)ー3.9倍
- 観光 :467名(149名)ー3.0倍
- 地域づ :483名(147名)ー3.3倍
- 情報科学:766名(183名)ー4.1倍
- 建築 :501名(112名)ー4.4倍
- 合計 :10,678名(2,762名)ー3.5倍
わずか10年で一般前期の志願者数が
2,685名から10,678名になっています。
なんと受験者数が3,976倍、約4倍にもなっているんです。
この数字のすさまじさは久留米大学の受験者数と比較すると分かりやすいです。
久留米大学の2012年度の一般前期の志願者は4,801名(医学部を除くと3,197名)
2021度入試は一般前期の志願者は5,977名(医学部を除くと3,943名)
医学部を含めたとしても
志願者数は4,801名から5,977名なので一般前期の受験者数は1.244倍
九産が3,976倍なのに対し久留米は1.244倍しか増えていないんです。
九産と久留米大学では大学の規模が違うのでこの数字だけで単純に比較はできるものではありませんが
九産大の異常な人気ぶり
倍率の高さは分かってもらえるはずです。
2012年度の入試難易度を振り返ると、九州産業大学よりも久留米大学に合格する方が明らかに困難でした。
しかし、現状を見ると、九産大の合格難易度は僅かながら上回っているように思われます。
今後、受験者数が大幅に減少することは考えにくく、九産大が過去のように誰でも容易に合格できる大学に戻る可能性は、少子化が現在よりも深刻化した場合に限られるはずです。
しかしながら、九産大に対する世間のイメージはそこまで変わらず、特に30代以上の世代では、「九産大=易しい大学」という認識が根強く残っているみたいです。
そうであっても、私個人としては、九州の大学の中で九産大を最も評価しています。
将来的に公認心理師を目指す場合や、九産大にしかない特定の学科(デザイン)を学びたいという明確な目的がある場合は九産を第一志望にするのはありです。
もちろん大学名にこだわりたいのであれば、西南学院大学や福岡大学を目指す方が賢明な選択となると思います。
合格最低点
九産は合格最低点が公表されていないので(もしかしたら近いうちに発表されるようになるかもしれません)。
何点取ればいいか分からず不安に思っている受験生も多いはずです。
少なくとも2012年はあの簡単な問題であっても臨床心理学科を除けば6割くらい取れればかなりの確率で合格できていたはずです。
学科によっては5割でも合格できていた可能性が高いと思います。
しかし、今は違います。
2021年度入試の合格者平均を見てください。
数字は左から順に
文系は英語・国語・日本史(合計)
理系は英語・数学・物理(合計)
生命科学だけ英語・国語・数学(合計)
です。
- 国際文化:85.8点・69.3点・78.7点(233.8点)
- 日本文化:73.6点・74.1点・83.8点(231.5点)
- 臨床心理:79.8点・75.7点・80.6点(236.1点)
- 子ども :75.6点・62.9点・74.1点(212.6点)
- スポーツ:74.0点・65.7点・75.9点(215.6点)
- 経済 :75.8点・64.0点・82.0点(221.8点)
- 経営流通:67.7点・63.5点・75.8点(207.0点)
- 観光 :71.2点・62.5点・75.6点(209.3点)
- 地域昼 :68.9点・66.6点・76.7点(212.2点)
- 情報 :71.2点・70.2点・81.5点(222.9点)
- 機械工 :62.9点・59.9点・74.1点(196.9点)
- 電気工 :58.7点・60.3点・75.2点(194.2点)
- 生命科学:72.3点・71.2点・63.9点(207.4点)
- 建築 :77.0点・75.6点・82.2点(234.8点)
- 住居 :71.2点・71.1点・80.9点(223.2点)
- 都市 :66.8点・66.0点・67.4点(200.2点)
になっています(芸術学部は除く)。
おそらく合格者平均から15点~20点マイナスした点数が合格最低点くらいになるはずなので
それがおおよその合格目安になると思っておけばいいと思います。
つまり、国際文化・日本文化・臨床心理・建築は7割とっても合格できるかどうか微妙なライン
その他の学部も6割で合格するのはかなり厳しい状況にあると思ったほうがいいと思います。
もちろん、受験年度によって問題難易度が異なるので、今年の合格者平均がどれくらいになるかわかりません。
なので、結局は結果を待たなければ分からないことに変わりはありません。
ちなみに、2012年の合格者平均は
国際文化が202.4点
日本文化が201.6点
臨床心理が219.6点
建築が196.1点
でした。
臨床心理はもともと合格するのがある程度難しく、国際文化・日本文化・建築はかなり難しくなっていることが分かります。
あと
合格者平均を書いて改めて確認できたのは
英語と選択科目ができるかできないか、合否を大きく分けるのはこの2科目にかかっているということです。
合格者平均と受験者平均を比べると国語ではあまり差がつかないのが明らかでした。
なぜ九産が人気大学になったのか
久留米大学は志願者数が増えず、九産だけが大幅に増えたのか、気になる人がいるようなので、私の考えを書いておきます。
まず、西南学院大学や福岡大学の合格難易度が上昇していることが、大きな要因として挙げられます。
これらの大学を志望する受験生にとって、浪人を避けるための第二・第三志望の大学を選ぶことが重要になります。
その際、多くの受験生の候補になるのが中村学園・福岡工業、九州産業、久留米だと思います。
ここで、福岡市内に住む受験生にとって、通学の利便性は大学選びの重要な要素となります。
久留米大学と九州産業大学を比較した場合、福岡市内からのアクセスの良さから、九州産業大学を選ぶ受験生が多いと考えられます。
さらに、ここ最近は九州産業大学の評価が向上していることも影響していると思われます。
以前は久留米大学を第二・第三志望として考えていた受験生も、九州産業大学を視野に入れるようになった可能性があります。
また、筑後地方と福岡市内の人口を比較すると、福岡市内の人口が圧倒的に多いため、この人口動態も志願者数の増減に影響を与えていると考えられます。
つまり、福岡市内の受験生が九州産業大学に流れることで、同大学の志願者数が増加し、久留米大学は伸び悩むという構図です。
これらの要因が複合的に作用し、久留米大学の志願者数が伸び悩み、九州産業大学の志願者数が大幅に増加したと考えられます。