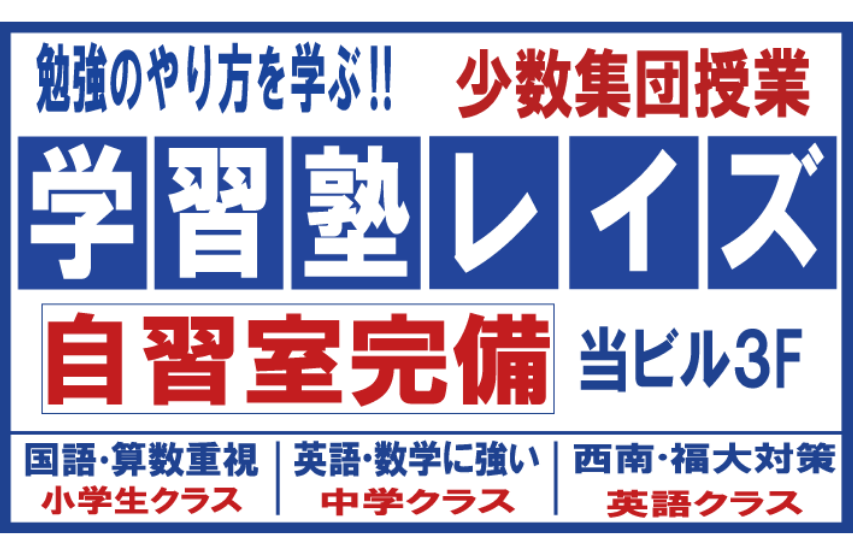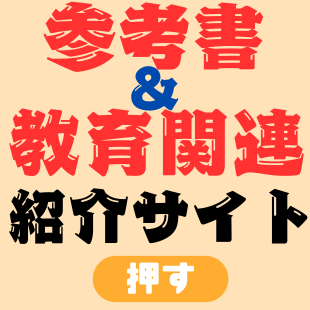日本史・世界史を選択科目に選ぶ子が大半なので、その2科目について書いています。
選択科目で迷っているのであれば、本格的に受験勉強を始める前に、どの科目が自分に合っているか参考書を読むなりして、一番取りやすいと思えるものを選ぶようにしてください。
目次
使う参考書
西南・福大の日本史・世界史で合格点(70点以上)を取るために最低限必要な参考書は次の2種類だけです。
- メインテキスト
- 時代と流れで覚える! 日本史・世界史
「メインテキスト」と「時代と流れで覚える」の2冊を使えば、西南・福大の合格点を取るために必要十分な知識を押さえられます。
あとは、必要に応じて一問一答、レベル別問題集、共通テスト過去問などを使って知識の定着を図ってください。
メインテキスト:200時間~
私が受験生であればメインテキストに
- 日本史:金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本
- 世界史:大学入試 茂木誠の 世界史Bが面白いほどわかる本
これを使います。
理由は2つあります。
一つ目、西南・福大が第一志望なのでオーバーワークになりそうな参考書(例えば実況中継)を使いたくないから。
二つ目、レイアウトが見やすいから。
このように、日本史と世界史のメインテキストは自分が一番しっくりくるものであれば、早慶などの難関私大を受験する人に向けたものや、簡単すぎるものでない限り何を使ってもいいと思います。
もちろん、「別に参考書使わなくても教科書でも大丈夫」というなら教科書でも構いません。
何を使ってもいいと言うと、「具体的に『これを使いなさい』と明確に指示してもらった方が助かる」と感じる受験生もいると思います。
しかし、一人ひとりの学習スタイルや教材との相性があるので、少なくともメインテキストに関しては自分に合ったものを使ったほうがいいです(ただし、「流れで覚える」は必須)。
私が「何を使ってもいい」というようになったのは次のような経緯があったからです。
以前、教科書で熱心に世界史を勉強している塾生がいました。
「参考書の方がもっと分かりやすいかもしれないよ」と当時の世界史定番に近かった『ナビゲーター』を渡し
翌日に「どう?」と、「教科書を使うのを止める」という返事が返ってくるだろうと確信をもって尋ねると
「教科書で…」とナビゲーターを否定されたことがありました。
このとき、自分がいいと思っているものが必ずしも全ての子に合うわけではないのだと痛感…。
以来、生徒に対して何かを特定して勧めるのではなく、「自分に合うものを使ったほうがいいよ」と、主体的な選択を促すようになりました。
参考書を買うときは、学校の先生に西南・福大受験でお勧めなものをいくつか教えてもらい、大きな本屋さんに行ってそれらを実際に読んでしっくりくるものを選ぶようにしましょう。
時代と流れで覚える!日本史・世界史:100時間~
メインテキストとは別に、「時代と流れで覚える!」を使うようにしてください。
この用語集は発売から20年近くたった今でも、用語暗記用の参考書として定番であり続けています。
長年、多くの受験生が使い続けているということは、内容が優れているからにほかなりません。
もし、西南・福大を第一志望にしている受験生でまだこの参考書を持っていない人は、すぐに購入したほうがいいです。
アウトプット用問題集(過去問・レベル別問題・一問一答):100時間~
日本史・世界史は覚えた大量の知識を定着させることが重要になります。
そのために利用するのが過去問や問題集です。
問題集は使わなくてもどうにかなると私は思うのですが、ほとんどの受験生は西南・福大が無料で配布している過去問だけでは演習が足りないと感じるはずです。
なので、よほど時間が足りないという受験生を除き、必然的に市販の参考書を使うことになると思います。
問題集は「共通テスト過去問」「レベル別問題」「一問一答 」など、西南・福大の問題レベルにあっているものならどれを使っても構いません。
一問一答を問題集に利用する場合は、メインテキストに山川の教科書を使っているのなら山川の一問一答、それ以外の参考書を使っているなら定番の東進ブックスのものを使えばいいと思います。
※ 一問一答は暗記用に使うのが一般的なので、過去問や問題集と同列で書くのはどうかとは思うかもしれませんが、知識定着のために利用するという位置づけと考えれば、過去問や問題集と同じなので、同列に扱うことにしました。
過去問を解き始める時期
非効率な勉強は避ける
個人差があるので何とも言えませんが、知識ゼロから西南・福大の日本史・世界史で合格点を取れるようになるために、そこそこ早い人でも400時間くらいは必要になると思います。

1日6時間勉強をすれば、たった2か月くらいで400時間を達成します。
直感的に「意外と楽かもしれない」と思うかもしれません。
しかし、そう甘くないのが現実です。
勉強をさぼってきた子が400時間くらい勉強をしたところで、その多くは合格点に達することはおそらくありません。
なぜなら、集中して勉強ができないからです。
集中して勉強ができなければ、集中して勉強ができている人が10分でできることに1時間くらい要することだってあり得ます。
そんな状況であれば400時間どころか1000時間勉強をしたと思っても結果が出るわけがないのは分かるはずです。
なので、合格したいのならただ勉強時間を増やすのではなく、「集中して勉強をする時間」を増やしてください。
また、仮に集中して勉強ができたとしても非効率な勉強をしていたら、時間のわりに思うような結果が出せません。
例えば、「参考書の文章を一言一句真似て書く」「資料の表を丁寧に書き写す」
もしこのような勉強をしているなら、入試当日までに合格点を取れるだけの暗記はできないと思ったほうがいいです。
受験勉強は、合格という明確な目標を達成するために、戦略的に取り組む必要があります。
それにもかかわらず「勉強をする」ということだけに意識が向き「効率的に勉強をする」ということを気にしていない受験生は意外と多いです。
ある程度勉強に慣れてきたら、非効率だと思うやり方を修正し、少しずつ自分の勉強を確立していってください。
限られた時間で効果的に学ぶ
進め方
私が普段暗記をするときにやっていることを勉強をするときにどのようにやっているのか書いておきます。
あくまでも私のやり方なので、受験生は勉強をやりつつ自分にとって一番やりやすいやり方を自分で探すようにしてください。
なお、使うテキストは、「金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本(以下、金谷)」と「時代と流れで覚える日本史用語(以下、流れ)」です。
- 1周目:金谷を小説を読むように流し読みをする(2年2月)
- 2週目:金谷・流れの暗記(2年3月~3年8月)
- 3周目:金谷・流れの暗記(3年9~11月)
学校の授業や模試の範囲に合わせて勉強はせず、11月末までに過去問で7割前後を取れるようにする。
3周目が終わったら、過去問を週1くらいで解いて弱点部分を把握しその個所を金谷・流れで確認、ということを繰り返す。
2週目・3周目の時の暗記の仕方は次の通り。
第1ステップ:範囲を決めて「金谷」を暗記をする
「金谷」を範囲を決めて読み進める(範囲は自分が好きなように決めていいが、各章の1部ごとでいいと思う)。
この時、「大切だ」と思ったこと(最初は赤字だけでもいい)を意識的に覚える。
大切だと思ったところは絶対に覚えるが、そう思わなかった部分に関してはなんとなく覚えるくらいでも構わない。
要は、この時点で完璧を求める必要はないということ。
第2ステップ:思い出す
一通り読み終え、ある程度覚えたと感じたら、何も見ずに覚えた内容を頭の中で再現する。
再現とは「歴史の流れ」「暗記した用語」などをできる限り思い出すこと、「自分なりにまとめる」ことと思ってもいい。
再現は頭ではなく、ノートに書いても構わない。
第1ステップでは第2ステップで覚えたことを再現することを意識して暗記をする必要がある。
仮に第1ステップで理解をしようとせず用語を丸暗記するだけでは、思い出そうとしてもほとんど何も思い出せないはず。
もし、思い出すことができなかったら、それは今までの勉強のやり方がまずかった証拠だと思ってもらいたい。
第1ステップでいかに覚えるかが重要ということ(最初は難しいかもしれないが、やっていれば自然とコツをつかめる)。
第3ステップ:再インプット(知識の定着)
第2ステップで思い出す作業をすれば嫌でも実感することになるが、思った以上に暗記ができていないと思うはず。
そこで、第1ステップで読んだものを再度読み直す必要が出てくる。
このとき、普段思い出す作業をしていなかった子は読み直しをするときに
「あ~、そういえばこれがあったな~」
「これ、最初読んだときよく意味が分からなかったけどこういうことなんじゃないかな?」
などと自分の脳内が普段と違う働きをしていること気づけるはず。
しかも、今までと異なり、知識が定着し、理解が高まることに驚きを感じる子もでてくるだろう。
第4ステップ: 「流れ」で知識定着&知識増強
「金谷」で一つの章が終わったら「流れ」の同じ範囲を赤シートで隠して解けるかどうか確認する。
例えば第2章の「弥生・古墳時代の日本」までを終わらせたら、「流れ」の2(弥生時代)・3(ヤマト政権の成立と外交)・4(古墳文化)をやる。
このとき、左右どちらのページも覚える
基本的のこの4ステップの繰り返しです。