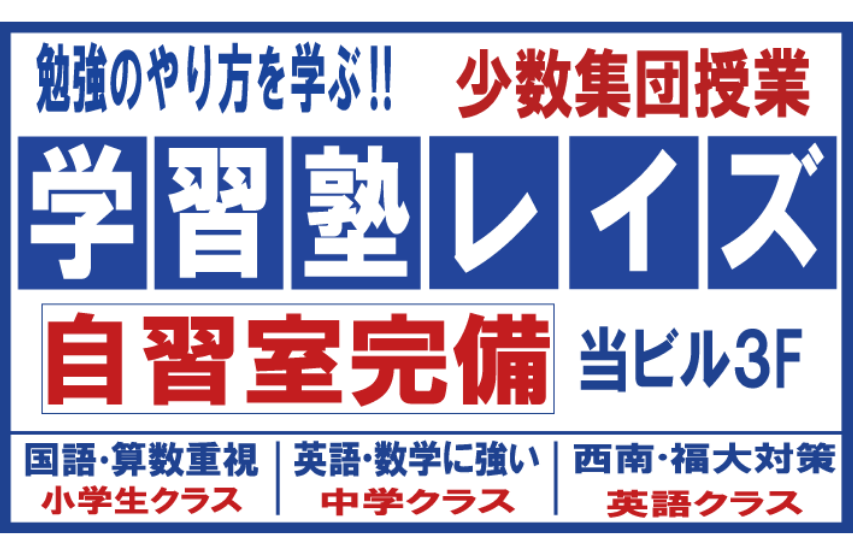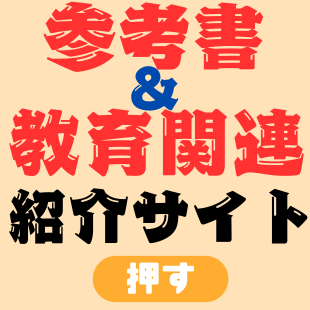「塾に通っているのに成績が伸びない」と悩んでいる場合
塾が子供たちにしてあげられることが何なのかを知ることが解決のヒントになるかもしれません。
目次
分かった気にさせるのは簡単
塾に通っている子が問題を解き間違えたとき
「塾ではできたのに」
「できるんだけどミスしただけ」
と言い訳をする場合は少し注意が必要です。
塾に嫌々通っている子や、学校の授業についていくのがやっとの子の場合
次のような対応で「勉強したつもり」にさせたり、「できる」と思い込ませることもできてしまいます。
- 解説授業の後に解く問題と全く同じ内容を授業で教えておく
- 「分からない」と言われたら答えを教えて空欄を埋めさせる
もちろん、「できる」という気持ちを持たせることは大切です。
しかし、塾が用意した問題を解くために必要なことを暗記させただけでは、本当の学力は身につきません。
そうならないように、うちの塾では
- 「なぜそれが正しいと言えるの?」
- 「それを答えにした理由は?」
- 「この選択問題はその選択肢が正解だけど、なんでこっちの選択肢はダメなの?」
- 「どういう手順で問題を解いたの?」
このような質問をしています。
生徒の中には「説明するのは面倒だ」「嫌だ」といった表情を見せる子もいますが
このような質問をすることで、生徒が分かっていないのに分かったふりをして先に進むことを防ぐことができます。
塾がやっていること
「塾に通っているのに成績が上がらない」
こんな悩みを抱えている子や保護者の方は少なくないかもしれません。
なぜ、塾に行っても成績が伸びないことがあるのでしょうか?
今回は、その原因をより分かりやすく理解してもらうために、
野球のピッチャー(生徒)とキャッチャー(講師)を例にとって、塾の役割を解説します。
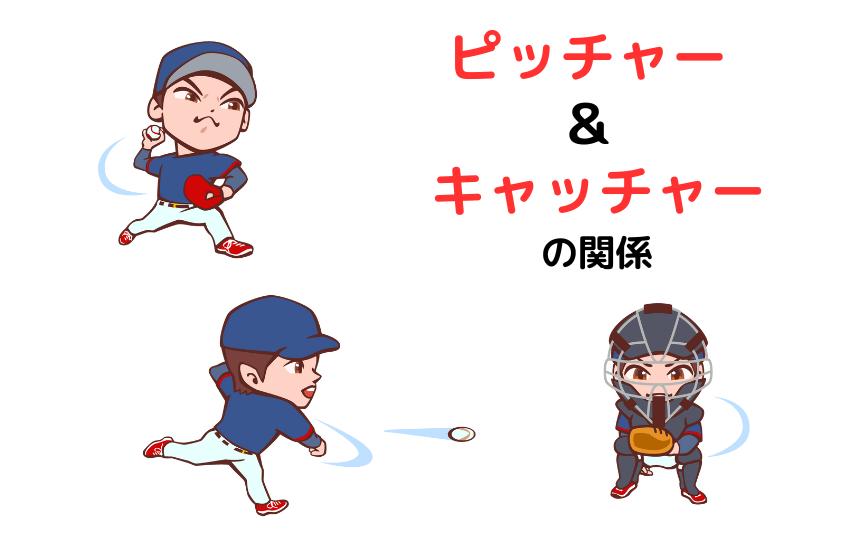
この記事を読めば、子どもが塾で最大限の成果を出すためのヒントが見つかるかもしれません。
塾講師は「導き手(キャッチャー)」
野球のピッチャーがどこに投げていいか分からず困っている時、キャッチャーは明確なサインを送り、最適なコースへと導きます。
これと同じように、塾講師は生徒が学習の迷路で道に迷った時、正しい方向を指し示すサポート役となります。
勉強が得意でない子どもの多くは
- 何から手をつければいいのか分からない
- どこが弱点なのか分からない
- どうすれば成績が上がるのか分からない
といった悩みを抱えています。
つまり
何をすればいいかわからないから勉強に手を付けられない
そんな状況に陥っているわけです。
膨大な情報の中で、自分にとって最適な学習方法を見つけ出すのは至難の業です。
ここで塾講師は、生徒一人ひとりの学力レベル、理解度、学習スタイル、そして目標を的確に把握し、可能な限り最適なカリキュラムや学習計画を用意します。
例えば、ある生徒が数学の応用問題でつまずいているとします。
塾講師は単に答えを教えるのではなく、なぜその問題が解けないのか、どの基礎概念が抜けているのかを丁寧に分析します。
そして、その生徒がどこに「球を投げるべきか」を具体的に示します。
それは、特定の公式の理解不足かもしれませんし、計算ミスを減らすための練習不足かもしれません。
あるいは、問題文の読解力に課題があるのかもしれません。
塾講師は、これらの弱点を見抜き、克服するための具体的なアドバイスを与え、練習問題を選定し、時には新しい視点を提供して、生徒が自分で答えにたどり着けるようにサポートしています。
生徒は「自らの球を投げるピッチャー」
しかし、どれほど優れたキャッチャーが的確な指示を出しても、実際にボールを投げるのはピッチャー自身です。
そして、ピッチャーが投げるボールの速さや正確さは、一人ひとり異なります。
ある生徒は、教わったことをすぐに吸収し、難しい問題も剛速球で正確にミットに入れられるかもしれません。
彼らは、生まれ持った高い能力、あるいはこれまでの積み重ねで培われた高い学習能力と集中力を備えています。
一方で、ミットに届かないほど球が遅かったり、あらぬ方向へ飛んでいってしまう生徒もいます。
彼らは理解に時間がかかったり、基礎的な知識の定着に苦労したりするかもしれません。
これは、学習全般において同じことが言えます。
塾講師は状況に応じて可能な限り最善の指導を提供し、学習環境を整えますが、実際にペンを握り、問題を解き、知識を吸収するのは生徒自身です。
どれだけ優れた解説を聞いても、どれだけ質の高い教材を使っても、生徒自身が積極的に学び、努力を重ねなければ、知識は定着しません。
剛速球を投げられる生徒は、自らの努力によってさらにその力を伸ばし、より高いレベルへと到達します。
一方、球が遅いと感じる生徒も、諦めずに練習を続けることで、少しずつコントロールを身につけ、球速を上げていくことができます。
塾講師は、生徒が学習において思うような結果が、何が原因だったのかを共に考えます。
そして、次こそは良い結果を出せるように、あるいはもっと速く、もっと正確に理解できるように、勉強のやり方を伝えたり、学習環境を整えたりしてサポートしていきます。
塾講師は「伴走者」であって「代行者」ではない
塾講師は、生徒が目標に向かって前進するための「導き手」であり、「伴走者」です。
決して「代行者」ではありません。
生徒の代わりに勉強してあげることはできませんし、生徒の代わりに試験を受けてあげることもできません。
野球の試合で、キャッチャーがピッチャーの代わりに球を投げることはできません。
キャッチャーの役割は、ピッチャーの能力を最大限に引き出し、勝利へと導くことです。
同様に、塾講師の役割も、生徒が自身の学習能力を最大限に発揮し、自らの力で目標を達成できるようにすることです。
学習は、生徒自身の能動的な行動と継続的な努力によってのみ実を結びます。
生徒の努力が報われるように、適切な道筋を示し、つまずいた時には手を差し伸べ、時には厳しく、時には優しく励まし、目標達成へと導いてあげる役割を担うのが塾講師なんです。
成績が伸びないのは塾だけの責任?
「塾に通って勉強をしているのに平均点を取れない」と悩んでいる子も大勢いると思います。
しかし、塾側も通塾だけで終わらせないよう指導しているはずなので、平均点に届かない原因は塾ではなく、自身にある可能性もあります。
塾に通っていること自体に満足してしまい
塾以外の勉強時間はゼロ
ということはありませんか?
上に書いた通り塾は生徒の代わりに暗記をしてあげることはできません。
定期テストやフクトで平均点を取るには最低限の暗記をしていることが絶対に必要なので
授業を受けるだけで終わっている場合は塾がない日もしっかりと勉強をするようにしてください。
そうすることですぐに平均以上を取れるようになるはずです。
ただ、少なくともうちの塾に通ってくれる子は5教科合計で平均点以下をとることは滅多にありません。
そう考えると塾側にも何か原因がある可能性もあります。
集団指導塾であれば周りの子がうるさくて授業になっていない
個別指導塾であれば問題を解いて丸付けしてもらうだけでほとんど何も教えてもらっていない、バイト講師と楽しくおしゃべりをするだけで終わっている
という状況があれば、それを許してしまっている塾側に大きな責任があります。
いずれにしろ、塾に通っているのに成績が伸びない場合、原因を探ればすぐに分かるものです。
自分に原因があるなら自分が変わるしかありませんし、塾に問題があると感じているのなら塾を変えることを考えなければなりません。
何十万円も払って授業を増やしても成績が伸びるとは限らない
授業は、必要な事項を分かりやすく、効率的に覚えるための手助けとなりますが、それを知識として定着させるかは生徒自身の努力にかかっています。
ただ授業を受けるだけで、復習や必要な知識の暗記を怠ると、かえって成績が伸び悩む原因にすらなりかねません。
そのため、成績が伸び悩んでいるときに「授業を増やせば改善するかもしれない」という気持ちはよく理解できますが、授業の量が必ずしも成績の向上に直結するわけではないという点には注意が必要です。
また、「有名講師の授業の方が成績が伸びる」というのも誤解です。
全国的に有名で人気のある講師の映像授業は、例外なく分かりやすいものです。
しかし、授業内容を理解するのは生徒自身です。
したがって、授業を聞いて理解する力がまだ備わっていない段階で受けても、授業を受けること自体が無駄になってしまう可能性さえあります。
当然のことながら、年間100万円の授業料を支払ったとしても、その金額が必ずしも授業の質に伴っているとは限りません。
結局のところ、本人が努力しなければ、いくらたくさんの授業を受けても、いくら高額な費用を払っても、それらすべてが無駄になるだけです。
成績を伸ばしたい、合格したいと思うのなら、何よりもまずは本気で勉強を始めることが大切です。