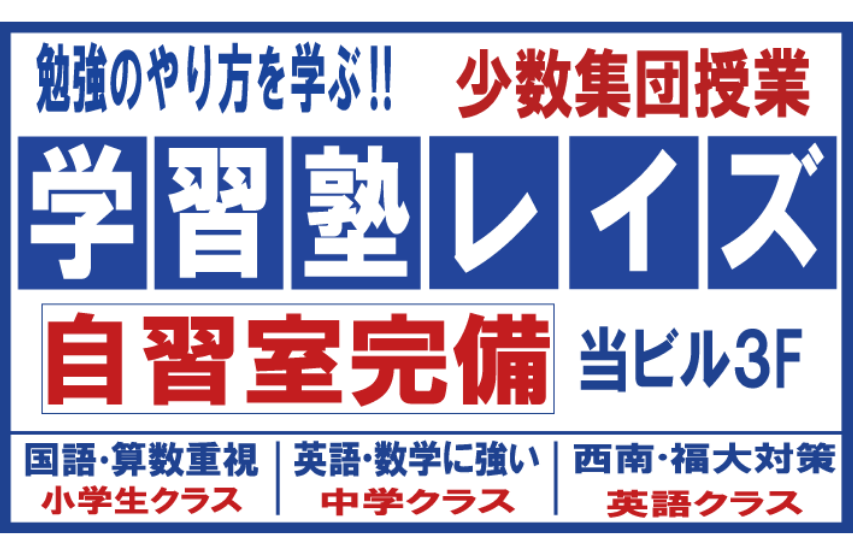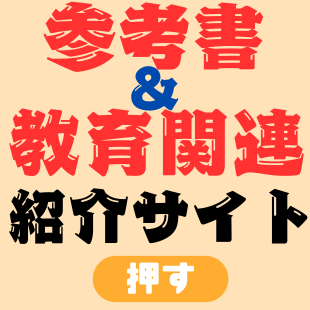高校生になると、学習内容が格段に難しくなるため(特に数学や物理)一概には言えませんが
公立中学校に通う中学生で平均点を取れていない場合
成績を伸ばすためにやるべきことはほぼ決まっています。
目次
定期テストで平均点に届かない主な理由は勉強量
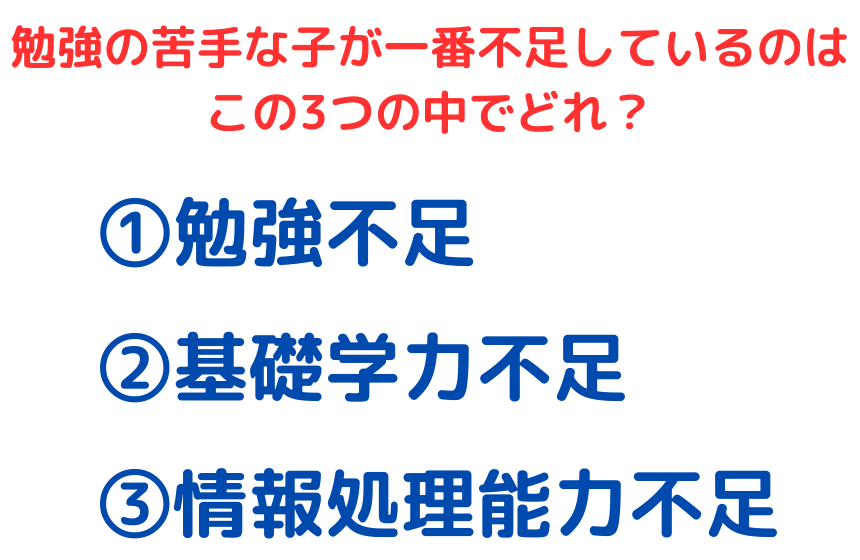
公立中学校の定期テストや中学2年生までのフクトのように
試験範囲が限定されているテストで平均点に届かない子の多くは
その主な原因が「勉強量の不足」にあると言えます。
つまり、覚えなければならないことを覚えていないから問題が解けないだけなんです(基礎学力も情報処理能力も結局は勉強をすることで得られるものなので当然と言えば当然です)。
限定された試験範囲のテストにおいては、定期テストで良い結果を出すためには、「勉強量」が最も重要です。
机に向かう時間が少なければ十分な暗記ができず、定期テストで結果を出すのは難しくなります。
例えば、普段全く勉強しない人が、テスト直前の1週間だけ1日に1時間程度勉強しただけで平均点を取るのは現実的に難しいでしょう。
また、「3時間勉強したつもりでも、ほとんど集中できておらず、実質30分も勉強していない」というケースもよく見られます。
時間をかけて取り組めば、必ず成果は現れます。
平均点以上を取りたいのであれば、まずはとにかく勉強時間を確保することに力を入れましょう。
塾に通っても成績が伸びない?
平均を取るためにどれくらいの勉強量が必要?
定期テストで平均点を取るのに必要な勉強時間には個人差があるので人によって大きく変わります。
なので「何時間勉強すれば平均点が取れる」と断言することはできないので、以下に示している時間はちょっとした目安と考えるようにしてください。
私の塾講師としての経験からすると
- 授業の内容を完璧ではないにしろ十分ついていけている
- テスト範囲表を参考に集中して勉強している
以上の2点を満たしていれば
5教科合計で25時間ほど勉強時間を確保できていれば、滅多なことでは平均点を下回ることはないです。
もちろん、これはあくまで目安です。
テスト範囲がものすごく広かったり、集中して勉強に取り組めない場合は、25時間どころか50時間勉強しても思うような結果が出ないこともあります。
付け焼刃の勉強で400点を目指そうとすれば、平均点を取るために費やした時間の1.5倍から2倍の勉強時間を確保しなければならないかもしれませんが、
逆に1日5分~10分を普段からやり続ければ、直前期に必要十分な対策をとるだけで400点以上を楽にとれてしまうことだってあります。
テスト期間に入るまでは部活や習い事で思うように時間を確保できないのであれば、「学校の授業時間を無駄にしない」ことが大切になります。
学校の授業時間を無駄にしなければ、家庭学習がゼロでも直前1週間の勉強だけで400点以上を取るのは思っているほど難しくないはずです。
勉強をしているのに結果が出ない?
よくあるのが、「3時間勉強した」と言っても、実はたった30分で終わるような内容にほとんどの時間を費やしているケースです。
これは、単に「机に向かっているだけ」で、集中して取り組めていなかったり、内容の薄い学習に終始しているためです。
「勉強しているのに成績が上がらない」と不満を漏らす子の多くは、この「勉強したつもり」になっている状態に陥っています。
もしこれに心当たりがあるなら、本気で集中して学習する時間を増やすだけで、成績は劇的に伸びるはずです。
集中できる環境にない
「勉強をしている」と思っているだけで実際には集中して勉強ができていない生徒は
- スマホが気になる
- 勉強をする一歩が踏み出せない
- 学習内容が全く分からにので手が付けられない
ことが原因であることが多いです。
このような場合、「勉強をするのが当たり前の環境」を作るために塾を利用することも考えてください。
上記以外の理由で集中して勉強ができない場合は
- 体調不良
- 睡眠不足
- 精神的なストレス
こういった問題を抱えていないか確認してください。
これらは、確実に集中力や認知機能を低下させます。
体調が悪いと感じたら、無理をせず休むことが大切です。体が回復すれば、自然と集中力も戻ってきます。
勉強時間を確保するために睡眠時間を削る学生がいますが、これは逆効果です。
集中力や記憶力の低下だけでなく、体調を崩す原因にもなります。
十分な睡眠は、学習効率を高める上で不可欠です。
親や友達との喧嘩や強い不安を感じる出来事など、精神的なストレスは学習への集中力を著しく低下させます。
ストレスを抱えていると感じたら、信頼できる人に相談するなど、適切な対処法を見つけることが重要です。
認知的な偏り
真剣に集中して勉強に取り組んでいるにもかかわらず、平均点を取るのも難しい子もいると思います。
この場合、
- 暗記力
- 理解力
- 推論力
- 計算力
- 空間把握力
- 情報処理能力
といった認知機能に何らかの原因があることも考えなければならなくなります。
短期記憶(ワーキングメモリ)が弱いと、口頭で説明されても内容を記憶にとどめ理解することが難しく、集団授業を受けても、何をやっているのか全く分からずに時間が過ぎるかもしれません。
長期記憶が弱ければ、単語、漢字、理科社会の用語、数学の公式を覚えては忘れ、覚えては忘れの繰り返しで、本気で覚えようとしているのにすぐに忘れてしまうかもしれません。
与えられた情報を体系的に整理したり、関連付けて理解したりするのが苦手だと、知識がバラバラになり、応用が利きません。
特に内容が複雑になると、暗記そのものも難しくなり、すべての科目でつまずく原因にもなります。
この場合、単語、漢字、用語の暗記が普通にできるため、定期テストでは400点くらい取れることがあっても、実力テストになると全く結果が出せないということが起こるかもしれません。
与えられた情報から論理的に結論を導き出したり、未知の問題に対して適切な解決策を見つけたりする力、つまり推論力が弱いと、応用問題や思考力を問われる問題に対応することが難しくなります。
苦手な原因が認知的な部分にあれば、努力ではどうにもならない可能性が高いので、
このような状況がみられる場合は、「何ならできて、何が苦手なのか」を把握することが大切です。
それを把握できれば、苦手なことをできるようにするのではなく、得意なことを伸ばすこともできるようになるからです。
ここで「得意なこと」は科目の勉強に限りません。
芸術的な才能があったり、好きなことに関してはものすごい集中力を見せるといった場合は、それに力を入れることもありだと思います。
ただし、認知機能の特性は専門的な知識がなければ、適切に把握することは難しいため、自己判断で「できない」と決めつけるのは危険です。
もし、学習面で気になる点がある場合は、公的な専門機関に相談することをおすすめします。